ホテルの閑散期とは?発生時期とその背景

ホテル業界における「閑散期」は、宿泊需要が通常よりも落ち込みやすい時期のことを指します。これは単に季節の問題だけでなく、立地や客層、さらには地域イベントの有無など、さまざまな要素が関係してくるんです。「なぜ今こんなに空室が目立つの?」と感じたら、それは“閑散期”に突入しているサインかもしれません。
シーズナリティによる宿泊需要の変動
宿泊業界では、時期ごとに明確な「繁忙期」と「閑散期」が存在します。たとえば観光地では、夏休みや年末年始といった大型連休は繁忙期ですが、それ以外の平日や季節の変わり目は宿泊数が減少する傾向があると言われています(引用元:https://www.plays-inc.jp/NKBF7yLC)。一方、ビジネスエリアでは逆に祝日や週末の方が稼働が下がることもあるようです。
つまり、シーズナリティ(季節性)はホテルごとに影響の出方が違うということですね。「春は忙しいのに秋は静か」なんてホテルも少なくありません。
地域や立地による違い
「観光地」「都市部」「空港周辺」など、立地によっても閑散期の現れ方はバラバラです。たとえば温泉地などは、平日になると宿泊客が極端に減ることがある一方、都市型ホテルでは、企業の動きに左右されることが多いようです。さらに、イベントやコンサート、学会などが開催される地域では、そのスケジュールに合わせて需要が上下するため、「いつも空いているわけではない」という特徴も見えてきます。
ビジネスホテルと観光ホテルの閑散期の傾向
ビジネスホテルは一般的に、週末や祝日に稼働が落ち込みやすいと言われています。出張需要が平日に集中するため、土曜の夜なのに空室が目立つ…なんてことも。反対に観光ホテルは、平日が閑散期となりがちです。家族旅行やグループ旅行の多くは休日に計画されるため、月〜木曜日などは集客に苦戦するケースもあるようです。
こうした違いを把握しておくことで、「なぜこの時期に売上が落ちたのか?」のヒントが見えてくることもあります。
#ホテル閑散期 #シーズナリティ #宿泊需要の変動 #地域特性 #ホテル経営
閑散期がもたらすホテル経営への影響とは

ホテル運営において、閑散期は避けて通れない課題のひとつです。特に繁忙期と比較すると来客数が大きく減少するため、経営面にさまざまな影響を及ぼすと言われています。ここでは、実際にどのような影響が考えられるのかを見ていきましょう。
客室稼働率の低下による収益減
閑散期に最も顕著なのが、客室稼働率の低下です。通常期には高い稼働率を維持できていたホテルでも、シーズンオフには半分以下まで落ち込むこともあると言われています。
例えば、観光地のリゾートホテルでは、ゴールデンウィークや夏休みといった繁忙期に比べて、冬季や平日は予約数が極端に減少するケースも見られます。このような状況が続くと、売上全体が大きく下がり、利益の確保が難しくなってしまうことが多いようです。
人件費や光熱費の固定費負担
売上が減っても、人件費や光熱費などの固定費は変わらず発生します。そのため、収益が少ない時期ほど運営コストが重く感じられることになります。
特に24時間対応のフロントや清掃業務などは、人手を削ることが難しい業務でもあります。施設規模が大きければ大きいほど、この固定費の圧迫感は大きくなると指摘されています。
リピーター獲得やブランド力低下の懸念
閑散期の影響は収益だけにとどまりません。リピーターの獲得機会の減少や、ブランド力の維持が難しくなるという側面もあります。
通常であれば、館内イベントやキャンペーンを通じてお客様との接点を増やし、ファンを増やすことができます。しかし、来館者が減ればその機会自体が減少し、SNSでの話題性も低下してしまうリスクがあると言われています。
これが続くと、競合との差別化が難しくなり、次の繁忙期へのスタートダッシュに遅れが出る可能性もあるのです。
#ホテル経営 #閑散期対策 #客室稼働率 #固定費問題 #ブランド維持
ホテルが実践している閑散期対策とは
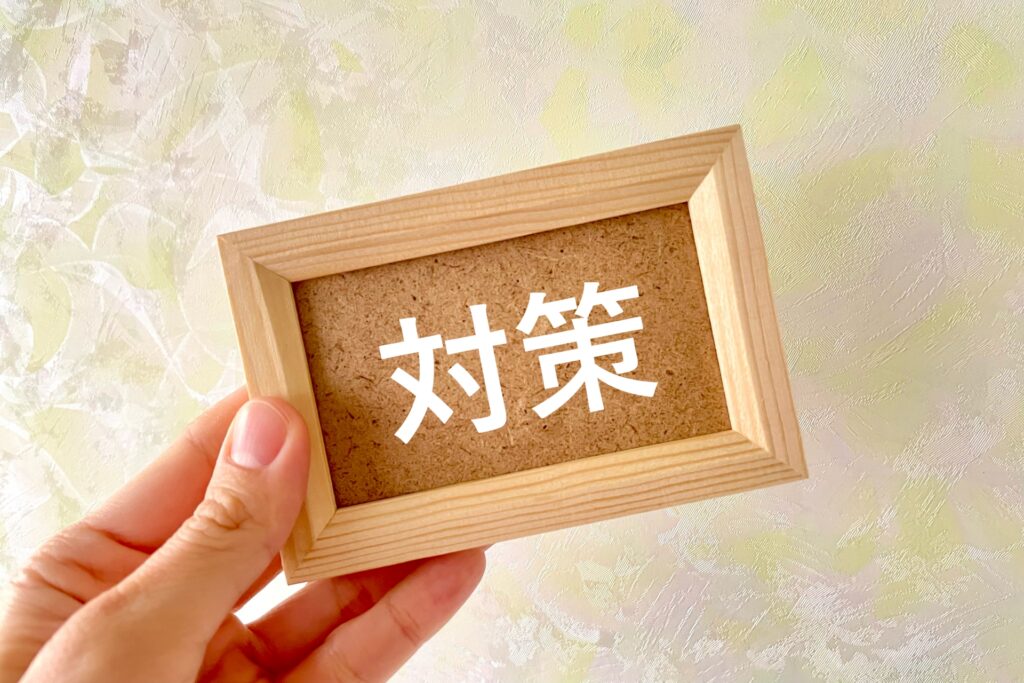
ホテル業界では、閑散期の売上減少をどう乗り越えるかが大きな課題となっています。ですが、実はこの時期こそ、新たな顧客層を取り込むチャンスでもあるんです。ここでは、いくつかのホテルで実際に行われている対策をご紹介します。<br>(参考:https://www.plays-inc.jp/NKBF7yLC)
平日限定の割引プラン・長期滞在向けプラン
閑散期の定番とも言えるのが、「平日限定」や「連泊向け」の割引プランです。
例えば「2泊以上で10%OFF」や、「チェックアウト時間延長サービス付き」など、小さな特典でも集客効果があるとされています。
最近では、ビジネスマンだけでなく、平日休みのカップルやシニア層からのニーズも高まってきているようです。
こうしたプランは、予約サイトでの表示順位を上げる施策とも連動しており、実際に「客室稼働率が回復した」という声も見られます(引用元:https://www.plays-inc.jp/NKBF7yLC)。
地元イベント・地域連携による集客施策
地域密着型の取り組みも注目されています。
たとえば、地元のマルシェや伝統行事に合わせた宿泊プランや、観光協会とのコラボイベントなどは「その時期ならではの魅力」を打ち出しやすいんですね。
こうした地域との連携は、ホテル単体では出せない価値を生み出すこともあり、「地域経済にも貢献できる」として評価されることもあるようです。
ワーケーションやリモートワーク需要の取り込み
そして近年特に注目されているのが、ワーケーション需要の取り込みです。
閑散期で空室が多い時期でも、Wi-Fi完備・静かな環境・仕事に集中できるスペースがあるだけで、「仕事+リラックス目的」の利用者が増えてきています。
あるホテルでは「1週間単位で予約できるワークプラン」を設けたことで、地方のフリーランスからの利用が増えたという事例もあるそうです。
価格を下げずに価値を上げる工夫として、「長期×仕事」の組み合わせがうまくはまった結果と言えるでしょう。
#ホテル閑散期対策#平日割引プラン#地域イベント活用#ワーケーション需要#稼働率改善施策
閑散期に成功しているホテルの事例紹介

ホテルの閑散期は、ただの「暇な時期」として過ごすにはもったいない時間です。実は、多くのホテルがこの時期を逆に「攻めのタイミング」と捉え、独自の工夫で集客や売上アップを実現しているようです。ここでは、実際に閑散期を乗り切っているホテルの取り組みをいくつかご紹介します。
低価格帯から脱却した高付加価値プラン
閑散期だからといって、単に「値下げ」で勝負してしまうと利益率が下がりがちです。その代わりに、ある地方のリゾートホテルでは「シェフによる地元食材フルコース付きプラン」や「1日3組限定・貸切温泉付きステイ」など、価格以上の価値を感じられるプランを展開。こうした取り組みは「価格競争から脱却し、ブランド価値を高めた成功事例」として紹介されることもあるようです(引用元:https://www.plays-inc.jp/NKBF7yLC)。
SNS・口コミ活用による集客アップ
最近では広告よりもSNSや口コミが大きな影響力を持つと言われています。あるホテルでは、閑散期限定の「インスタ映えルーム」を設け、宿泊者が自然にSNS投稿したくなるような空間作りを実施。その結果、フォロワー経由での予約数が増え、広告費をかけずに新規顧客を取り込んだそうです。リアルな体験が共有されることで、信頼性の高い情報として広まるという流れが見られます。
食・体験など地域資源を活かしたパッケージ化
観光地以外でも注目されているのが「地域の魅力と組み合わせた体験型プラン」です。たとえば、農業体験や味噌づくり、地元ガイドと巡る歴史散歩など、滞在そのものに「物語性」を加える工夫がされています。宿泊だけではなく、その土地ならではの体験を提供することで、滞在価値が高まり「また来たい」と思わせる動機につながると評価されているようです。
#ホテル閑散期対策#高付加価値プラン#SNSマーケティング#地域体験プラン#宿泊業経営改善
閑散期をチャンスに変えるためのポイントまとめ

ホテル業界では「閑散期=売上が落ちる時期」と捉えがちですが、実は見方を変えることで新たな可能性を引き出せるとも言われています。価格を下げて集客する方法もありますが、それだけでは持続的な利益にはつながりにくい側面があります。ここでは、閑散期を有効に活かすための3つの視点をご紹介します。
価格競争に頼らない「価値提供」の設計
「安ければ泊まってくれる」という時代ではなくなりつつあります。むしろ、価格以外の魅力に重きを置いた「体験価値の提供」が求められているようです。たとえば、季節限定の地元食材を使った料理や、滞在中に参加できるワークショップなど、「その時期ならでは」の特別感があるプランは好評だと言われています。価格を下げる前に、宿泊者にとって価値ある時間を提供できるかを見直すことが大切です(引用元:https://www.plays-inc.jp/NKBF7yLC)。
顧客目線でのニーズ分析と新サービス開発
実際に宿泊したお客様の声や、予約サイトのレビュー、SNSの投稿などから、顧客がどんな体験を求めているかを把握することが有効だと考えられています。閑散期だからこそ、トライアル的に新しいサービスを導入するチャンスとも言えるでしょう。例えば、女性向けの美容アイテム付きプランや、親子連れ向けのアクティビティ付きプランなど、ターゲットごとの需要に合わせた施策が注目されています。
定期的な販促と評価指標の見直し
効果的なプロモーションは単発では終わりません。特に閑散期には「見つけてもらう」ことが一層重要です。SNS広告やメルマガ、地域媒体との連携など、小規模でも継続性のある告知が鍵になります。また、キャンペーンの効果測定も忘れてはいけません。客室稼働率だけでなく、口コミの増加や再訪率といった多角的な指標を取り入れて、PDCAを回すことが成果に直結しやすいと言われています。
#ホテル閑散期対策#価値提供型マーケティング#顧客ニーズ分析#閑散期プロモーション#宿泊体験の差別化









コメント